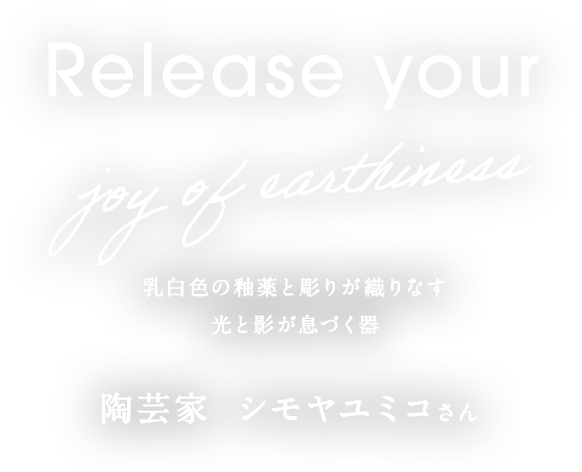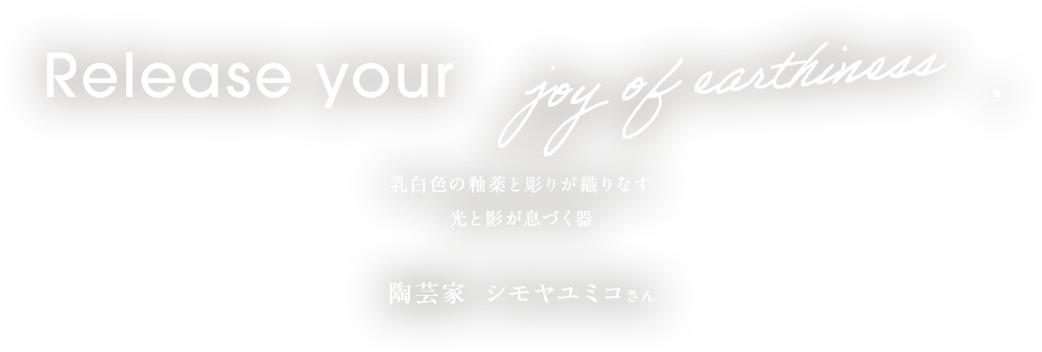落ち着いた佇まいの中に、
彫りと乳白色の釉薬(ゆうやく)が生み出す
豊かな表情を秘めた器。
陶芸家・シモヤユミコさんの作品は、
釉薬や土の質感だけでなく、器の表面に施された
繊細な彫りが印象的です。
彫りによって生まれる光と影の微妙な揺らぎが、
器に深みと表情を与え、
手に取るたびに新たな魅力を感じさせます。
今回は、その制作の過程や想いをうかがいました。
シモヤさんの場合は、彫りの表情を引き立てる独自の釉薬を調合しており、器一つひとつに個性と深みを生み出しています。

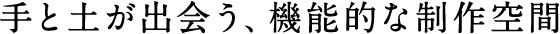
お話を伺ったのはシモヤさんの工房。コンパクトながら効率よく作業できるよう整えられ、シモヤさんらしいセンスが光る居心地の良い空間です。時折、窓の外から電車の音が届き、静かな制作の時間に穏やかなリズムを彩ります。
シモヤさんの作品づくりは、まず土をこねて空気を抜いて粘りを均一にする「菊練り」の工程からスタート。その後、ろくろで成形し、少し乾かして器の表面に手彫りで彫りを施します。最後に素焼きした器に釉薬をかけて再度焼成する――このような一連の工程を経て、一点ずつ丁寧に生み出されます。工房では、その制作の流れを再現しながら、細やかに解説してくれました。

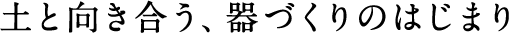
「土は笠間と信楽の土をブレンドしています」とシモヤさん。後ほど詳しく触れますが、茨城県にある陶芸の産地、笠間はシモヤさんが陶芸を学んだ地です。「笠間の土は歪みやすいので、お茶碗や花器など、ろくろで作る作品が多くなるんです。成形前には“菊練り”という作業で粘土から空気を抜きます」菊練りは体重をかけて粘土を練るため、体への負荷が大きく、とても重労働。体への負荷を減らす工夫は、陶芸を長く続けるために欠かせません。そのため機械も併用しながら、粘土を成形しやすい状態に準備します。

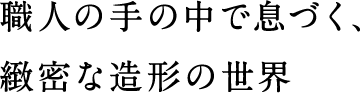
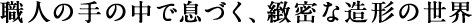
菊練りを終えた粘土を手に取り、シモヤさんはろくろでお茶碗を作って見せてくれました。ろくろの前に鏡を置き、正面だけでなく全体の形やバランスを確かめます。「ろくろで形をつくること自体は比較的、簡単なのですが、同じフォルム、大きさのものをいくつも作るとなるとハードルが高くなると思います」粘土が指先の動きに応えるように変化し、あっという間に美しいお茶碗の形に整っていく――その様子はまるで魔法のようです。しかし見た目の軽やかさとは裏腹に、手のひらと指先で粘土の中心をしっかり押さえ形を整えるには力も必要。指先の微妙な力加減と体重のかけ方が絶妙に絡み合い、一つの塊の粘土が手の中でスムーズにお茶碗へと変わっていくその過程に、職人の技術と感覚の緻密さを感じます。

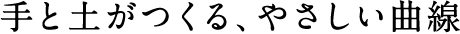
次に見せてくれたのが、半乾きの状態で再びろくろに乗せて表面をそぎ落とす「削り」の工程。この削りによって、底の厚みや全体のシルエットを整え、手にしっくりとなじむ美しいフォルムへと仕上げます。高台(こうだい)も彫り出していきます。これも長年培ってきた手や指の感覚がとても重要で、職人技が光る工程です。微妙な力加減やリズムのもと、美しい器へと目の前で整えられていきます。「個展が近くなると、削りで出た粘土がろくろ周辺の床に積み重なって、それを踏みながら作業することになるんですよ笑」

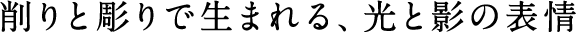
そしてフォルムが完成した器に、いよいよ彫りが施されます。今回は、お茶碗の表面に「面取り」という模様を施す様子を見せてくれました。まず大きめに面を削り取った後、細かな彫りを重ねて稜線を際立たせ、光と影が美しく映える表情を作り出します。道具は先端の形状が異なる輪ガンナを使い分け、力を入れる部分と抜く部分を巧みに組み合わせながら、器に繊細な彫りの模様を刻んでいきます。完成した面取りは、器の形そのものを引き立てながら、触れたときにも手にしっくりなじむ立体感を感じさせる仕上がりです。

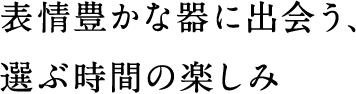
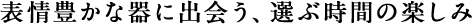
彫りの深さや稜線の微妙な角度まで計算された手さばきは、軽やかに見えても高い集中力と力の調整が必要です。「彫りが一番好きな工程です。一度、手首が腱鞘炎になってしまって、それからは作業は1日8時間まで、週に2日は休むと決めているのですが、彫りの作業に集中しすぎてしまって、気付いたら外が真っ暗…ということも度々です。先日も花器を彫り始めたら、夜中の11時になっていました笑」シモヤさんの器は、彫りのない無地を含め彫りのパターンは5種類。器の形やサイズとの組み合わせで、豊かな表情を生み出しています。自分だけの一つを見つける過程も、シモヤさんの作品の魅力のひとつです。

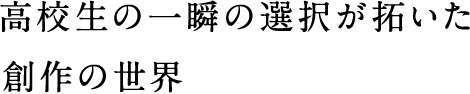
陶芸に魅了されたシモヤさんの、陶芸との出会いは、思いがけない偶然からでした。「高校生の修学旅行で、いくつかの体験コースの中からたまたま陶芸を選んだんです。全然うまくはできなかったけれど、その楽しさは心に残りました」20代で書籍や雑誌のデザイナーとして働きながら、趣味で陶芸教室に通い始めます。土に触れている時間が心地よく、気づけば週末は教室に入り浸るほどに。やがてフリーランスになり多忙のため一度は陶芸から離れますが、仕事のペースを落として再開すると、再び夢中になり没頭するようになったそう。「陶芸で生計を立てている人がいると知って、本格的に陶芸家を目指そうと決めたんです」偶然の出会いから始まった土との関わりは、いつしか人生の軸へと育っていきました。

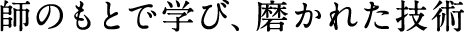
笠間の窯業指導所に通い、ろくろを学び始めたシモヤさん。夜は陶芸家・額賀章夫さんに師事し、卒業後もおよそ2年間、額賀さんのもとで経験を積みました。「最初は片付けや釉薬の処理といった雑用からでしたが、次第に彫りの作業も任せてもらえるようになり、最後には作る・削るといった一連の工程すべてを経験させてもらいました。とても忙しい日々でしたが、私が学校に通い始めたのは35歳の頃。ゆっくり勉強している余裕はない、と焦っていたので、この環境はむしろありがたかったんです」

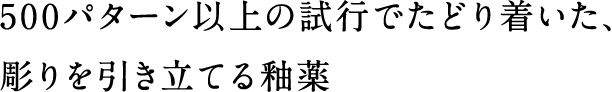
その後は釉薬の研究に本格的に取り組むため、改めて学校に入り直し、釉薬科で1年間学びます。「彫りを施す作家さんは多いですし、市販の釉薬では表現に限界があると感じました。オリジナリティを出すために、彫りを引き立てる独自の釉薬を追求しました。同じ原料でも成分の違いで仕上がりが変わる世界ですから、付け焼き刃では通用しない。だからこそ、徹底的に勉強しました」「釉薬はグラム単位で成分の配合を調整します。本当にわずかな差で、マットになったり透明になったりするんです」シモヤさんは500パターン以上もの配合テストを重ね、理想の釉薬を完成させました。「笠間の土でなければ同じ発色は出せません。土に含まれる成分と反応して色が生まれるんですね。本当に奥が深い世界です」

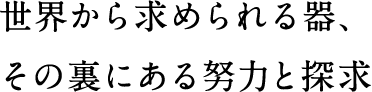
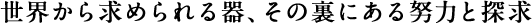
そうして生まれた作品は、土の温もりと釉薬の奥行きを静かにたたえ、いまは国内のみならず海外でも注目を集めています。ドイツや台湾など世界各地から声がかかり、ニューヨークのギャラリーからは「もっと大きな作品を」とリクエストされることも。「大きな花器が欲しいといったお声をいただいています。ただ、大きくなるほど制作は難しくなります。力も技術もより必要になるので、他の陶芸家のもとを訪ね、大きな作品を作るための技術を学んだりもしています」手に取って見せてくれたのは500mlの缶ビールがまるっと入る大きなビアマグ。釉薬の効果できめ細かな泡が立ち、追加購入するファンも多いアイテムです。「アメリカのお客様はこれで朝、スープを飲むんだそうです!」

シモヤさんの創作意欲は尽きません。現在、長年愛用している釉薬とは別に、新たな釉薬づくりにも取り組んでいます。
「忙しくて、なかなか釉薬に集中する時間がとれないのが悩み」と語るシモヤさんですが、
その背景には、陶芸の世界ならではの材料の変化への危機感があります。
「私は完成した釉薬をこれまで10年、使い続けてこられましたが、他の作家さんからは、同じ釉薬が作れなくなったという話も聞きます。
釉薬の材料の原料が変わってしまうのも、この世界では起こりうること。
この1色で10年続けられているのは、奇跡に近いのかもしれません。だからこそ、新たな釉薬も必要だと感じています」
シモヤさんの作品に触れるには、個展や陶器市への出展が絶好の機会です。
最新の出展情報はInstagramで発信されています。
ぜひチェックしてみてください。心を込めて生みだされたシモヤさんの作品に、きっと出会えるはずです。

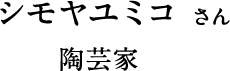
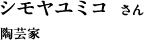
KIDIにてグラフィックデザインを学び、出版業界で約10年間デザイナーとして活動。その後、本格的に陶芸の道へ進む。茨城県笠間で陶芸を学び、額賀章夫氏に師事。2012年に独立し、現在は藤沢に工房を構える。日々の暮らしにそっと寄り添う器を中心に作陶している。